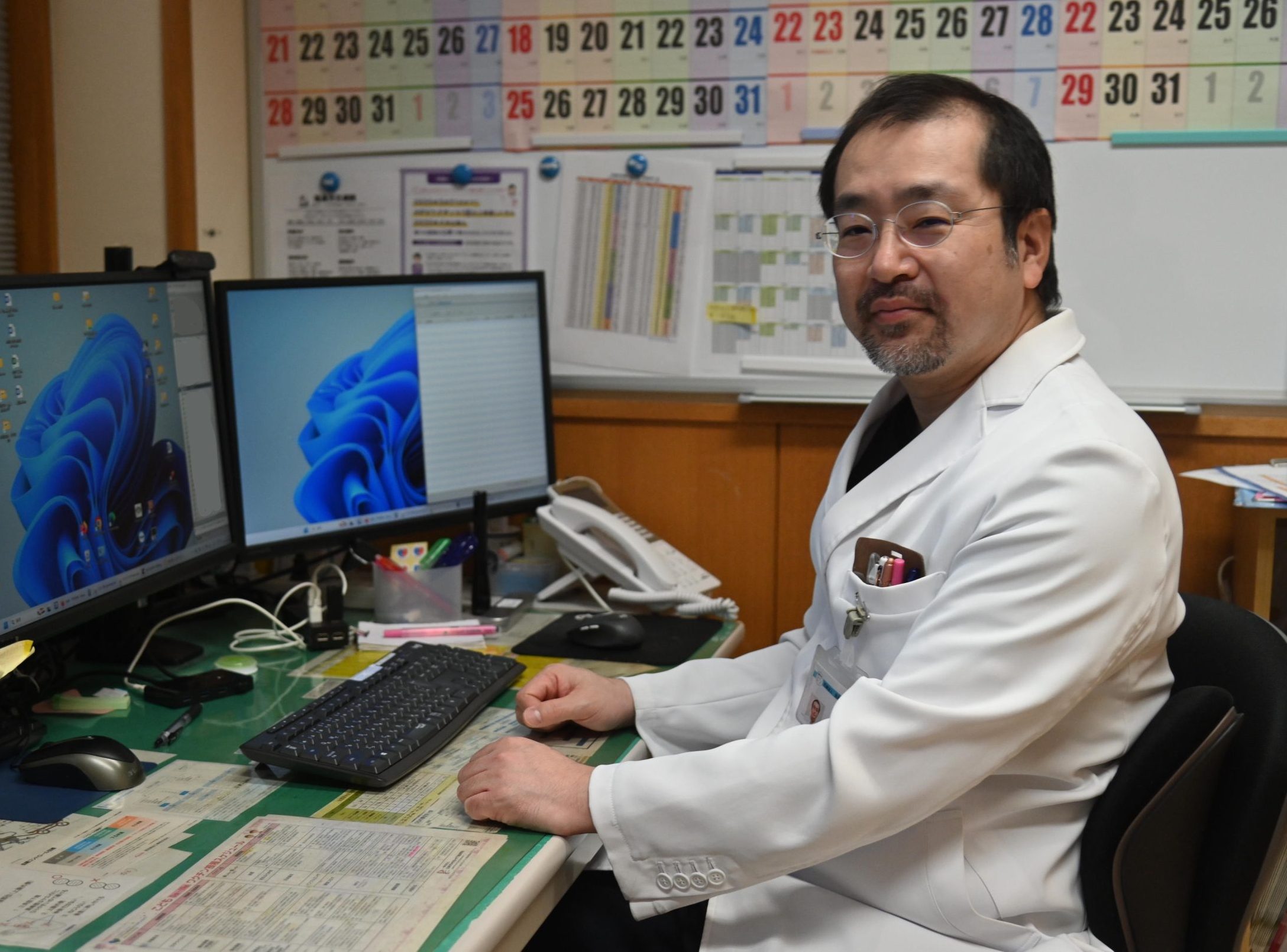いわき市にある医療法人医和生会介護保険部で定期的に実施している「合同研修」は、職員一人ひとりの学びと成長を支える大切な取り組みです。現場での実践に活かせるテーマを選び、立場や年齢を超えて意見を交わすことで、多職種が連携しながらよりよいケアを目指しています。
本年度3回目の今回は「身体拘束」をテーマに注意点をみんなで再確認。部署や年齢の垣根を超えたグループワークで意見交換し、理解を深めました。


● 事前アンケートして企画
職員の知識やスキルを高めようと、各介護事業所の代表職員で構成する「研修委員会」が主催。これまでコロナ禍で中止していましたが本年度11月に再開し、2月の2回目に続いて今回は5月14日に開かれました。担当職員2人が講師を務め「身体拘束について〜あなたのその対応、合っていますか?」と題して講話。事前に各事業所に身体拘束の疑問をアンケートし、全部署から上がった「スピーチロック」を中心に研修内容を編成し工夫。グループワークも取り入れ、参加した介護職員約40人が部署や年齢をバラバラに6テーブルに分かれて話し合いました。


● 3つの弊害
講師を務めたのは、やがわせデイサービスの岡部と小規模多機能型さらいの谷江。2人は「身体拘束がもたらす3つの弊害」として、身体的、精神的、社会的のそれぞれの弊害を解説。「原則、身体拘束は法律で禁止されている」と強調した上で、3つの条件を満たし慎重な手続きを踏んだ場合のみやむを得ない身体拘束もあるとも。その3つの条件は「切迫性」「一時性」「非代替性」で、その各観点をスタッフで慎重に検討する大切さを呼び掛けました。

● 「離床センサーは身体拘束?」
事前アンケートの質問に答える具体例の紹介では「離床センサー、着床センサーの使用」「玄関の施錠、エレベーターの利用制限」はいずれも身体拘束に当たるのかを取り上げました。前者については職員が「楽をするため」に使われている場合は身体拘束に該当する可能性があり、ご利用者様の行動意欲や安全を支援する目的で使用されていれば該当しない、と説明。後者は、特定のご利用者様を対象にして行動を制限するものではなく、不特定多数の安全確保を目的とした対応であるため、原則として身体拘束には当たらないと解説しました。

● 「スピーチロック」の予防
「三大ロック」として、物理的に行動の自由を奪う「フィジカルロック」、睡眠薬や精神薬を過剰に摂取させる「ドラッグロック」、言葉で身体・精神的な行動を抑制する「スピーチロック」を紹介。そのうち事前アンケートで一番質問が多かった「スピーチロック」を丁寧に説明。「ちょっと待ってください!」という声掛けは、ご利用者様に「なぜ待つの?」「命令されている」などと感じさせてしまうと注意しました。予防のため「優しい口調」「具体的な内容の伝達」「スピーチロックが発生する環境をつくらない」の3点を上げました。

● グループワーク
グループワークでは、「ちょっと待って」「どこ行くの?」「部屋で横になってて」というスピーチロックに当たる言葉をどう言い換えるといいかを話し合い。事例では「職員がご利用者様の食事介助中、認知症で歩行時ふらつきのある別のご利用者様がソワソワして席から立ち上がろうとしている。この時、どんな声掛け、対応をするか」を考え合いました。

● みんなで意見を共有
参加者はテーブルごとに、最近ハマっていることを交えて自己紹介。部署や年齢の違いによる意見の一致や違いに気づくなど、和やかな雰囲気で話が進んでいました。グループの発表もあり、参加者全員でアイデアを共有。「ちょっと待って」の言い換えでは「〇〇しているので、5分ほどお待ちください」など丁寧さ、具体性などを考慮した意見が出て、事例では「『どうしました?』と確認し、急ぎでなければ『終わるまでお待ちいただけますか?』と、緊急性があれば周りのスタッフに応援を呼ぶ」といった対応策が出ていました。

次回の合同研修は8月、「介護保険制度」をテーマに行われる予定です。
<介護保険部の本年度の合同研修の記事>
第2回「コンプライアンス」>>>
第1回「褥瘡の予防」>>>
\「家で過ごせて本当によかった」その一言が、地域に寄り添う福祉の原点/
医和生会では、「在宅での暮らしを支えたい」「家族も含めて寄り添いたい」という思いを持った介護職員を募集しています。
利用者様の人生に向き合い、人と地域を結びつける介護の仕事に、あなたもチャレンジしてみませんか?
▼ 職場見学・応募はこちらから
医和生会の採用情報ページ|https://iwakikai.jp/recruit/