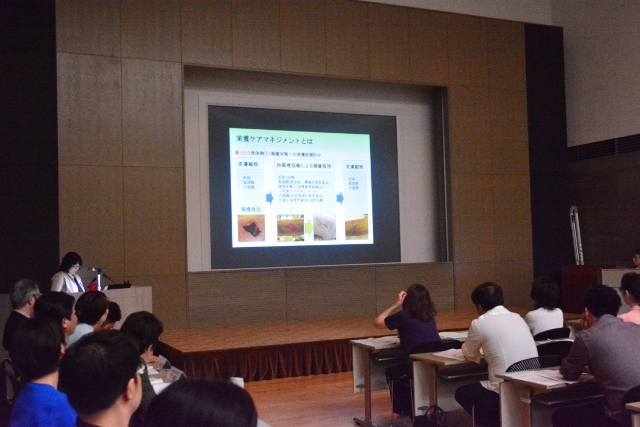医和生会グループの専門職が日ごろの看護や介護の成果を発表した21日の「ケア事例発表会」。社会福祉法人いわきの里の管理栄養士・大川原由子さんが「多職種連携・多職種協働における管理栄養士のかかわり」と題して事例を発表しました。管理栄養士は、医師や看護師、介護職、介護支援専門員(ケアマネジャー)らとご利用者様の状態をパソコン上で情報を共有。連携を図りながら栄養管理と食事形態の調整に努めています。

↑ほかの専門職と一緒にご利用者様の水の飲み込み具合を確認する大川原さん(中央下)=2017年8月25日
● ご利用者様の情報 多職種が共有
いわきの里では、介護サービスの質の向上のため、食事栄養や安全、行事、接遇など9つの委員会・会議を設置。さらに、施設長、主治医、看護師、介護士、ケアマネジャー、管理栄養士らが、ご利用者様の情報をパソコンで共有しています。この委員会での話し合いとIT化を生かし、大川原さんはご利用者様ごとに栄養ケアマネジメントに取り組んでいます。ご家族の希望も含めさまざまな専門職の意見を共有し、栄養ケア計画を作成します。医師や看護師、介護士がご利用者様の褥瘡(じょくそう)を発見すれば、多職種協働でケアします。栄養面では、食事・水分摂取量、栄養量を増やすなど、医師や看護師と連携しながら検討し、皮膚の再生に配慮した食事を提供しているといいます。
● 職種ごと意見「食事量は?」「誤嚥は?」
摂食・嚥下(えんげ)障害のあるご利用者様には、経口維持をチームで支援します。主治医の指示、計画の作成、ご家族への説明、経過観察、嚥下機能を確認する水飲みテストなどを経て支援計画の原案を作成。その立案作業では専門職種が意見交換し、問題点を見つけます。パソコンで共有している実際の一部画面を見せ、大川原さんはある患者様のケースを紹介します。そのケースでは、看護職と介護支援専門員(ケアマネジャー)が日常生活動作(ADL)の低下による食事量を懸念、管理栄養士は誤嚥の可能性を警戒し、介護職は食事量と嚥下状態の両方を危ぐし、連携によってあらゆる視点から意見が出ます。それを受けて、食事形態、とろみ剤の強弱を見直し、口腔ケア、食事介助の必要性を検討します。
● ご利用者様一人一人に合った食事を
管理栄養士としてできることは食事形態の工夫です。最後まで口から食べられることを目標に、見た目、食べやすさ、安全を考えてソフト食を導入。さらに、果物だけ飲み込めないご利用者様にはそれを流動食に、飲み込みがうまくできず途中で残すご利用者様には高カロリームースを付けて栄養確保するケアも。「今何が必要かを考えながら、安全第一に個別化を図り微調整しています」と大川原さん。ソフト食でも、焼き物の場合はバーナーで焦げ目を付けて常食に近づける工夫も。「食べることは生きる事。ご利用者様に残さず食べていただくことが目標」と語りました。
【ケア事例発表会の過去記事】
<2019年>
「笑って死ねる在宅療養を目指して・岩井里枝子医師の基調講演」
<2018年>
<2017年>
<医和生会(いわきかい)の求人・採用情報>
医和生会は1年以内の新卒離職率0%!新卒フォロー面談や「若手ラボ」といった教育支援を通して、若手職員の定着につなげています。
https://iwakikai.jp/recruit/