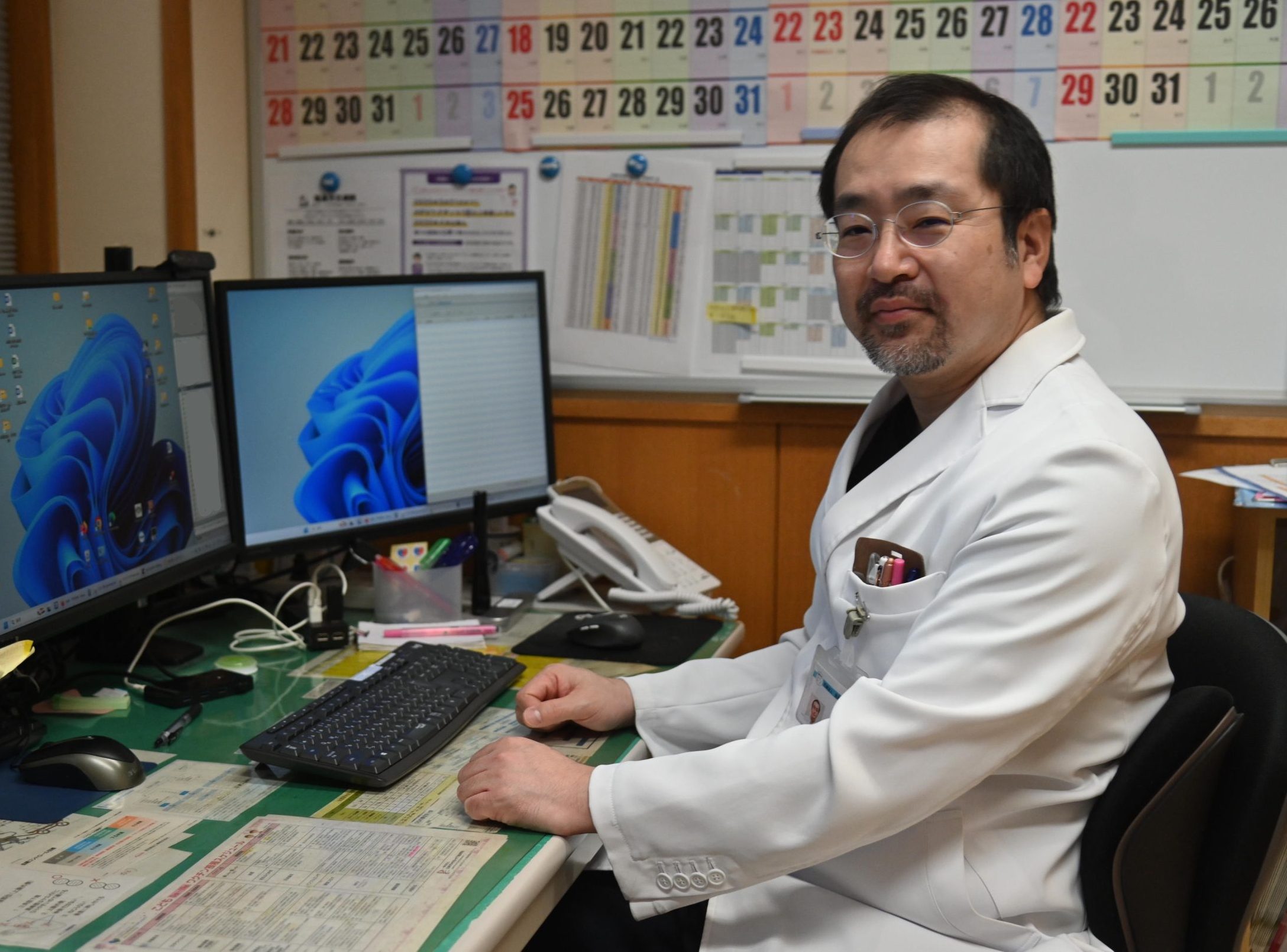いわき市平地区の医療・介護・福祉関係者が交流する「平在宅療養多職種連携の会」がこのほど、オンライン上で開かれました。発表した地域包括支援センターの職員が認知症支援をテーマに、平地区で活躍する地域サポーター「チームブルー」の事例を紹介。認知症の方の「社会参加」を促す大切さを訴えました。
● 本年度の計画を承認
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護職員、リハビリ職など30人が参加し、4月24日に開催。前段、事務局を務める平地域包括支援センターの職員が同連携の会の事業目的や内容を改めて説明。本年度の年間計画で、大きな会場で多くの医療・福祉関係者で交流する「多職種連携のつどい」を11月か12月に開催する案も承認されました。
● 国の基本計画を開設
平地域包括支援センターの認知症地域支援推進員が「認知症バリアフリーの取り組み〜チームブルーの活動報告」と題して発表しました。発表者は、去年12月に発表された国の「認知症実施推進基本計画」の概要を取り上げ。項目「共生社会の実現を目指す」に記載された「『新しい認知症観』に立つ」を深く解説し、「話せない」「危険重視」などネガティブなイメージが先行される「古い認知症観」ではなく、「本人視点」「支えられる一方でなく支え合う」といった「新しい認知症観」への考え方のアップデートの必要性を説きました。

● 「チームオレンジ」とは
その後、認知症の方を地域住民で支える「チームオレンジ」の紹介もしました。チームの3つの基本では、ステップアップ講座を修了した認知症サポーターがいる、認知症の方がチームの一員、困りごとに早期から継続して支援できる、というポイントを列挙。そうしたチームを組んで、地域住民や多職種の専門家、生活関連企業などと連携して支援していく指針が示されているといいます。
● 平地区で活躍する「チームブルー」
いわき市では「チームオレンジ」が2チーム活動中。そのうち、「チームブルー」という名前で活動している「チームオレンジ」の事例も紹介されました。2023年8月にステップアップ講座の受講生有志で発足され、現在15人が拠点を設置しない個別支援型のタイプで活動。具体的にスーパーでお買い物客らを交えての講習会、オレンジカフェ、デイサービスでの交流研修、個人宅に訪問する出前支援などの活動が紹介されました。最近では毎月1回、スーパーで誰でもゆっくり会計ができる「スローショッピング」の取り組みも行われているといいます。
● 社会参加が大切
「高齢者でも社会参加できることが人との繋がりや満足感が得られ、役割を果たし自尊心を持てる」と社会参加の大切さを強調。社会参加は認知症の診断前後から困難になるといい、社会参加を阻害する大きな要因は認知症の偏見とも。「社会参加の促進」は医療・介護分野では支援するのが難しく、サポートできる社会資源の必要性を訴えました。
● 質疑応答
民生児童委員は「訪問活動すると認知症ではないが同じ話を繰り返す孤立の方がいる。このままでは認知症になるのではと思うが、この方を早期と言っていいか、どこに相談すればいいか」と質問。発表者は認知症の予備軍と思われると指摘し、「1人になってお話しない環境は認知症につながる。本人が望むならオレンジカフェなどに出て社会参加を促してほしいし、包括支援センターに繋いでほしい」とアドバイスしました。薬剤師は「薬局の窓口で認知症の疑いを感じる患者様もいる。その時は職員間で共有し、主治医などに相談する」と早期発見の取り組みを紹介し「『家族と来てほしい』と考えて古い認知症のイメージを持ってしまう」と課題も交えて、本人ができることを尊重する大切さの気づきを得ていました。
同連携の会の山内俊明会長(山内クリニック院長)は、認知症になるならないに関わらず、一定の年齢になったら趣味の場などに出て社会参加するのが大事と予防策を出し、みんなで協力して支え合う大切さを呼び掛けました。
<平在宅療養多職種連携の会・関連記事>
「複合問題世帯の支援」
「睡眠時無呼吸症候群を学ぶ」
「最期の望みをかなえた訪問看護の支援を学ぶ」
「行政書士から見た認知症対策」
「心不全を考える」
「多職種の情報共有を考える」
「いわき市の地域医療の課題を学ぶ」
「データ連携、介護報酬を学ぶ」
「口腔の健康チェック 専用シートで確認法学ぶ」