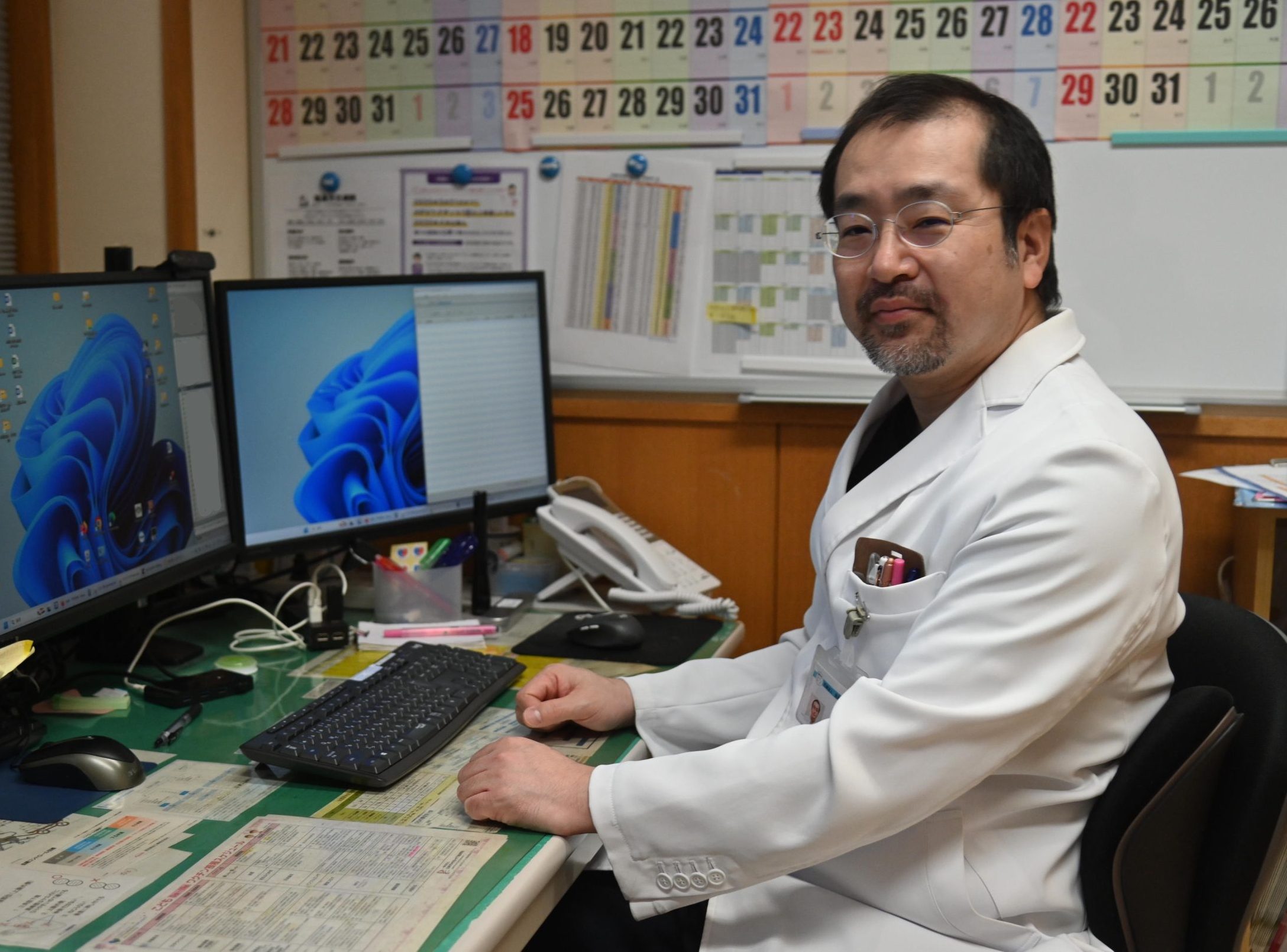いわき市平地区の医療・介護・福祉関係者が交流する「平在宅療養多職種連携の会」がこのほど5年半ぶりの対面となり、いわき市の文化センターとオンライン上で開かれました。在宅訪問医が地域高齢者の医療をテーマに事例を発表。参加者は医療や介護だけでなく生活や住まいなど複雑な課題と向き合うため、多職種連携の大切さを改めて確認しました。
● 久しぶりの対面
同連携の会は2020年1月を最後にコロナの感染予防で休止しました。それでも情報交換し連携を続けようと、同年7月からオンラインで再開。コロナ禍が明けて久しぶりの会場での開催に戻った今回は6月19日に開かれ、対面での交流が行われました。

● 高齢者医療の実情
この日は医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護職員、リハビリ職など約35人が参加。発表した訪問医は「地域高齢者の全人的医療」と題して講話しました。「高齢者医療の実情」の話題では、救急搬送の件数が増加傾向にある総務省のデータを紹介。約半世紀前は交通事故による搬送が多かったが、現在は緊急性が低い軽症での搬送が大半になってきている特徴を解説しました。さらに、受診の2、3割は病気ではなく、虐待や貧困といった社会的要因が原因といわれ、それにより疲弊するご家族のメンタルケアも必要になり、高齢者虐待の通報や相談も増加傾向にあると注意を促しました。
社会的な課題を抱えている高齢者が増えているため、入院後の退院先の調整が困難になっているとも指摘。生活保護や介護の申請、家族が不在のため住居の確保など、医師も病気を治す以外の業務が増えてきていると医療を維持する苦しさを訴え。救急要請を受けても、かかりつけ病院との非効率な情報共有や人材不足などで受け入れが困難だと理由を上げました。

● 見守り、生活支援、住まい
そのほか高齢者在宅医療の課題では、労働人口の減少でも質を保てる医療体制の構築と、医療の効率化、連携強化の必要性を指摘。「コロナ禍の在宅医療」「在宅医療と高齢者の住まい」の話題にも触れました。超高齢化社会を迎えるにあたり、「見守り」「生活支援」「住まい」の重要性を説きました。
● 質疑応答
質疑応答では、参加者から「近所の認知症の高齢者が真夜中に『息子に虐待された』と家にくる。そのご家族には虐待の様子は感じず、誰にどう報告すればいいか」と質問。発表者は「外来の場合は訪れたご家族の介護の辛さを聞いて初めてアドバイスできる」と傾聴の大切さを上げ「わざと上半身を見てアザがないか確認する場合もある」とも。地域包括支援センター職員は「真夜中に来る点からご家族が大変苦労しているのでは」と推測し「包括支援センターに相談してほしい」と呼び掛けました。
同多職種連携の会の山内俊明会長(山内クリニック院長)は「医療や介護、お金、住まいだけでもない様々な問題がある。こうして色々な職種が集まり、困ったことがあればみんなで解決の糸口を見つけることができる。これからもみんなで力を合わせていきましょう」とまとめました。
<平在宅療養多職種連携の会・関連記事>
「在宅医療が使えない自宅看取り」
「認知症の取り組みを共有」
「複合問題世帯の支援」
「睡眠時無呼吸症候群を学ぶ」
「最期の望みをかなえた訪問看護の支援を学ぶ」
「行政書士から見た認知症対策」
「心不全を考える」
「多職種の情報共有を考える」