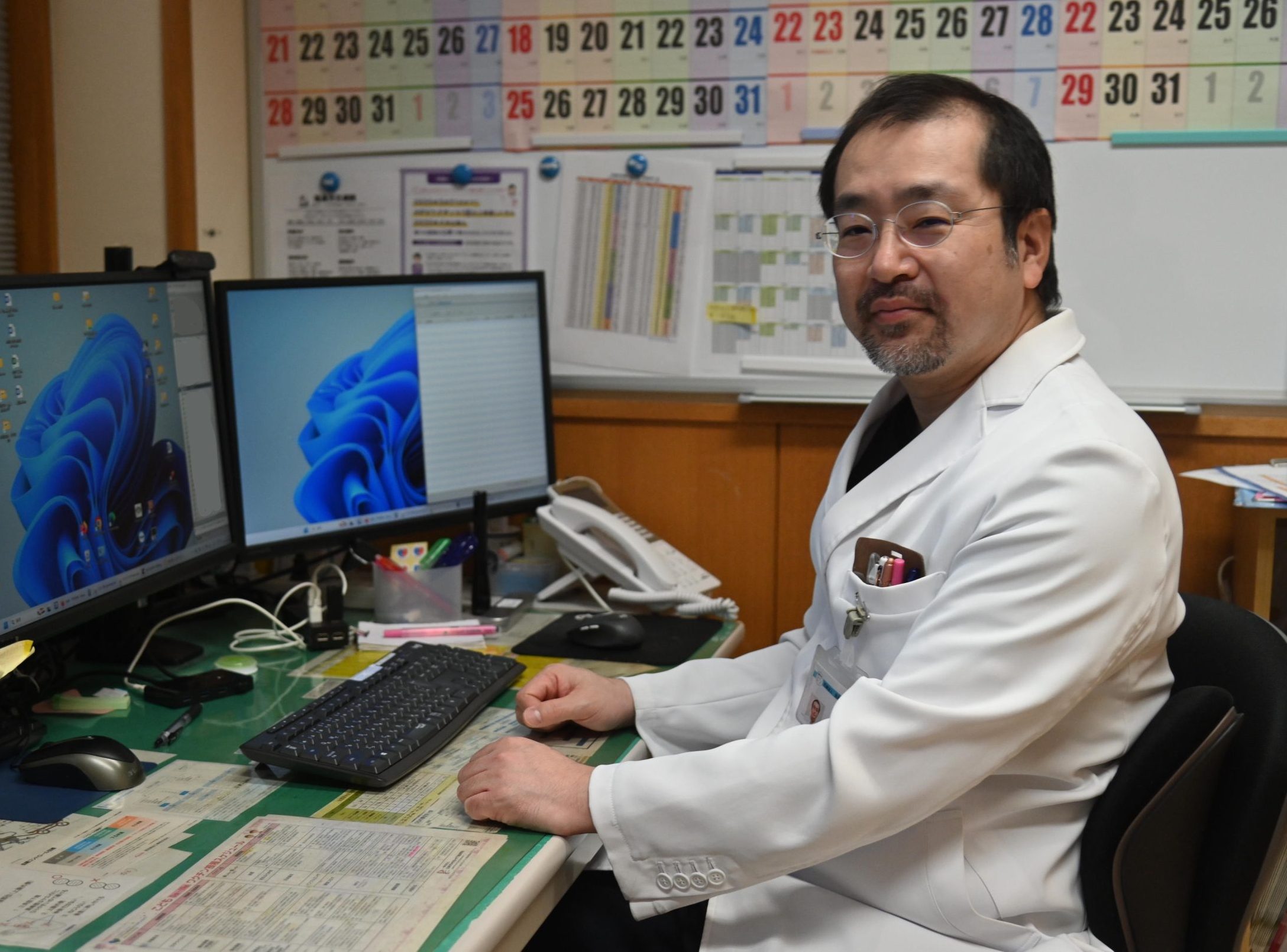2018年6月、いわきの医療を守るため、会長職のバトンを受けたいわき市医師会の木村守和新会長(木村医院)。
「医師不足」の解決に向け、医師同士の連携、多職種の連携、市民への呼び掛けに力を入れる考えです。
「やれることは何でもやる」と決意する木村新会長に意気込みを聞きました。

↑「やれることは何でもやる」と決意するいわき市医師会の木村新会長
<いわき市医師会の木村守和会長インタビュー>
―会長になられた現在の心境は?
介護保険・在宅医療担当として医師会の役員を16年ほど務めてきました。
東日本大震災後の6年前には副会長職を頼まれ「自分のできることでは、できる限り貢献したい」と引き受けました。
会長となる今は「やるしかない」という思い。
医師会を取り巻く問題には、簡単なことは一つもありません。
医師不足が最も重要な問題ですが、可能な限り医師同士およびいろんな職種同士がつながり、さらには市民にも理解してもらって乗り切っていくしかない。
医師会のトップを務めるのは非常に責任が重いものであると、身が引き締まる思いでいます。
―いわき市の地域医療面での課題は?
「医師不足」が一番。
勤務医が不足して高齢化しています。
さらには医療職員も介護職員も少ない。これを改善するために、いわき市に医師が来てもらえるような取り組みをしていきたい。
10年20年先のいわきの医療が続くようにしていくのが最大の課題です。
―医師不足対策はどうお考えですか?
まだ副会長だった今年4月に、さまざまな地域の医師・各診療科の医師・病院の医師を大勢集めて「医師不足対策委員会」を開きました。
医師同士が医師不足の現状を正しく認識し、問題意識を共有して連携に努めることが重要です。
他の地域から医師がいわきに行きたいと思うような連携を創り出したいです。
医師不足対策委員会を中心に相談して、医師を呼ぶためにやれることは何でもやるしかないと思っています。

↑市民公開講座で登壇した木村新会長(左から2人目)=2018年6月2日、いわき市の産業創造館
―いわきに行きたいと思うような連携とは具体的にどのようなものでしょうか?
一つ考えているのは、いろんな医療機関のネットワークで作る総合診療医養成プログラムです。
臓器別医療というような専門志向がある一方、病気だけではなく患者を全体的に診る総合診療も注目されています。
かしま病院でも総合診療医の研修を行っていますが、これをもっと大きな取り組みにできないかと考えております。
東北では宮城県に「みちのく総合診療医学センター」があり、大きな成果をあげています。
いわき市でも、大きい病院・中小病院・診療所などいろんな場所で総合診療の勉強ができる環境をつくりたい。
これから関係者と相談していろんな医療機関が連携する総合診療プログラムをつくり上げ、「いわきに来たらいい研修ができる」というアピールをしたい。
初期研修には市立総合磐城共立病院に8~9名が来ていますが、2年の初期研修後にも残ってもらえるようなプログラムがつくれるといいですね。
研修医だけではなく、総合的な医療を学びたいと思っている専門医にとっても魅力的であるともいます。
「いわきに関係はないけど、面白そうだから行ってみよう」という医師が増えてくれるといいですね。
―「在宅医療ネットワーク」も昨年つくりましたね。
厚生労働省は療養型の病床を減らして在宅医療に移そうとしています。
いわき市では在宅医療をやるパワーも決して多くはないと思っています。
このネットワークの目的は、市内で在宅医療を中心的に取り組んでいる9人の医師を在宅サポート医にして、在宅医療をこれから少しでもやってみようと思う医師を支えるものです。
20年以上通院してきた患者さんが通院できなくなって往診や訪問診療を頼まれた時に「このサポート体制があるから私もやってみよう」と思ってほしいです。
―多職種連携の面ではいかがお考えでしょうか?
在宅医療は医師だけでやるものでなく、いろんな職種と連携するのが大事です。
東京大学と柏市が連携した多職種研修をモデルに、おととし「在宅医療推進のための多職種研修会」を始めました。
▶在宅医療推進へ「市民への啓発」課題・いわき市「多職種研修会」で情報共有
▶講義やグループワーク通し多職種連携・「在宅医療推進のための研修会」
今年も今月第4回研修会を開催します。
いわき市医師会としては、多職種連携の形成にかなり力を入れていると思います。

↑「主治医意見書説明会」で多職種連携について講話した木村新会=2018年2月15日、いわき市のパレスいわや
―木村会長は認知症対策にも熱心でいらっしゃいます。
認知症は80歳以上になると珍しいことではなく、一定の方たちが認知症になることは避けられないと思います。
いわき市は先進地域に比べると、認知症に対する市民の見識がそれほど高まっているとはまだ言えないと思っています。
それを打ち破るため、7月上旬に「いわき市介護事業所協議会」を立ち上げて認知症対応サポート部会をつくることになりました。
この協議会はいわき市のすべての介護事業所が集まる組織を目指しており、介護従事者の多くは認知症の対応に関わっています。
その中で意欲のある方々がプロジェクトチームをつくり、地域に出て認知症の講座を開いたり、研修をしてケアの質を高めたりしていきます。
そういった活動に厚みが出て、広い地域をカバーできるようにしたいです。
―地元の四倉・久之浜大久地区で児童の認知症教育にも力を入れているようですが。
認知症を知っているかどうかで初期の対応がだいぶ違ってくるので、教育は大切です。
四倉・久之浜大久地区では「認知症絵本教室」に取り組んでいます。
対象の小学校4年生は前向きにピュアな気持ちで聞いてくれます。
「認知症の人はどんな気持ち?」「どんな対応ができる?」をテーマにディスカッションすると「一緒に買い物してあげる」といった心優しい答えが返ってくる。
そういう認識で大人になってもらうことは大事です。
そして子どもから親にパンフレットをわたしてもらって、親の世代に認知症についてお知らせする波及効果も期待しています。
市内に児童の認知症教育を広げるため校長会にも声を掛けて、取り組みを全市的に広げていきたいです。
―最後に意気込みをお聞かせください。
第一には、医師不足対策のため医師会会員の力を今まで以上に結集して引き出すことです。
第二には、関係機関・多職種とのつながりを強めることです。
第三には市民に対して医療について語っていくことです。
「在宅医療出前講座」や「いわき医療介護学校」など、様々な職種が市民に働きかける教室がありますが、もう少し医師が街に出て医療の話をするようにしたいと考えております。
このような取り組みを通して、市民の皆様にも医療や介護の知識を持ってもらい、対応力が上がっていくことで、病院のかかり方や疾患罹患率などで大きな改善につながると考えています。
将来「やれることがあったけど、やらなかった」と思いたくないです。
責任は重いですが、やっていくしかないと思っています。