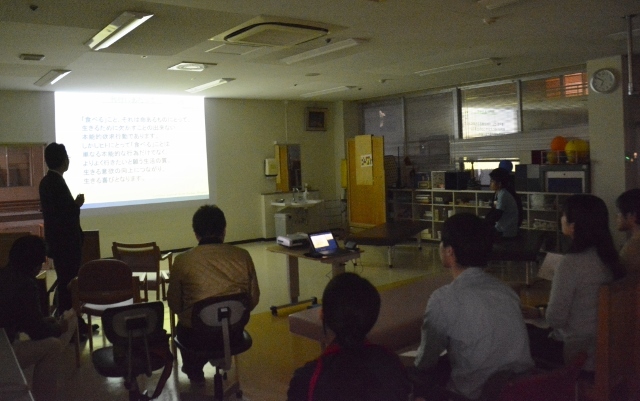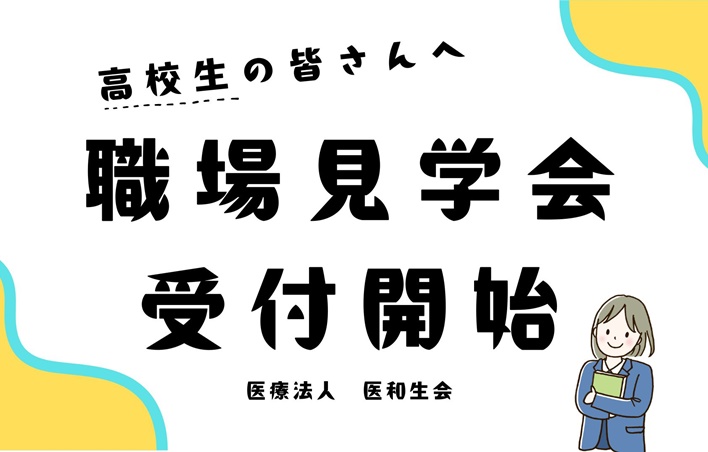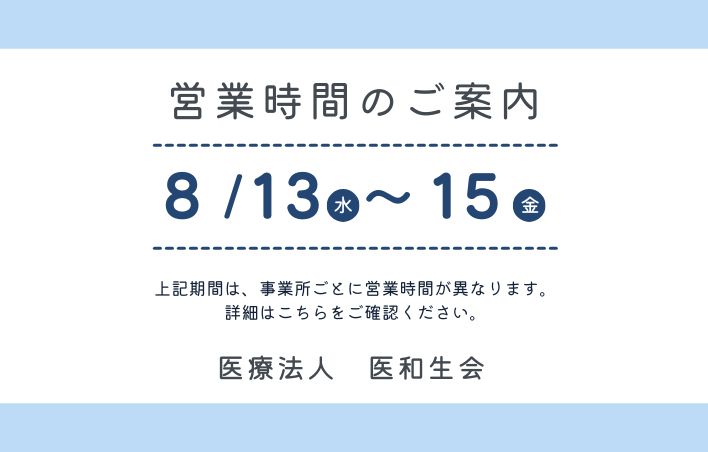「食」をテーマに介護を考える「いわき食介護研究会」がこのほど、いわき市のかしま病院で開かれました。講師を務めた常磐病院の外科医で医学博士の神崎憲雄先生が「食べることは生きること」と題して講話。直接体外から胃に管を通し栄養を入れる「胃ろう(PEG)」や摂食嚥下(えんげ)治療に携わる神崎先生は、延命措置と見られ敬遠されるようになった「胃ろう」を「すべて悪だと思わないで」と警鐘を鳴らすとともに、生活の質の向上と寿命を伸ばすために「食べる」という行為の重要性を訴えました。
● 幅広い意味を持つ嚥下障害
3月28日に開かれた勉強会には、医師、歯科医師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、介護支援専門員(ケアマネジャー)、リハビリ職ら約40人が参加。神崎先生は、食べ物を口から食道を経て胃に入れるまでの運動を嚥下とし、「食べる」ための器官の欠如や損傷で嚥下障害になるという基本的な意味を解説。「食欲がわかないのも嚥下障害」とその障害の幅広さを説明しました。食べ物が気管に入る「誤嚥」と食べ物以外の物を飲み込む「誤飲」の違いにも触れ、人間は気管と食道が交差する複雑な「のど」を持ち、このつくりを持つ生物は人間だけと話しました。
● 「胃ろうは特別優れた延命治療ではない」
嚥下障害の患者への胃ろうの是非についても語った神崎先生。胃ろうなどが患者の尊厳を損なう可能性があれば治療を差し控える必要性を表明した「日本老年医学会」の立場(2012年1月)や、胃ろうによって悩む患者を取り上げた新聞記事などを紹介して「胃ろうが『悪』のように扱われている」と指摘しました。その一方で、かしま病院での胃ろう患者412人を調査したデータを基に、胃ろう後の平均寿命は507日で患者の45%が1年以内に亡くなっていた点から「特別優れた延命治療ではない」と説明。さらに、胃ろうによる合併症は5%以下だったという特長も挙げました。神崎先生は「私見」と前置きし「食べられるうちに行うべき」と胃ろうの早めの判断を呼び掛け。口から食事も取れる胃ろう患者は、胃ろうだけで栄養を摂る患者よりも寿命が長かったことから、「栄養をしっかり摂りつつ、嚥下機能を保つことが大切」と訴えました。
● 食介護研究会 1997年に発足
「いわき食介護研究会」は1997(平成九)年、食べる側の目線に立った介護を考えようと誕生。いわき市内の歯科医・故市川文裕さんが「食介護」という造語をつくり立ち上げました。2016年までの3年間は活動を休止していましたが、去年再開。市内の医師、歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、リハビリ職者らが集まり、患者が「食」を楽しめるケアを追求して研鑚を積んでいます。
【関連記事】
【医和生会(いわきかい)各事業所では、胃ろうを含めた医療処置に対応しています】
<関連情報>
\「いわき 看護師 求人」でお仕事検索中のあなたへ!/
詳細な仕事内容や給与、応募方法はこちらから。医和生会(いわきかい)では、現在9職種で職員募集中です。私たちと共に、地域社会に貢献し、やりがいある「医療・介護・福祉」の仕事に挑戦しませんか?