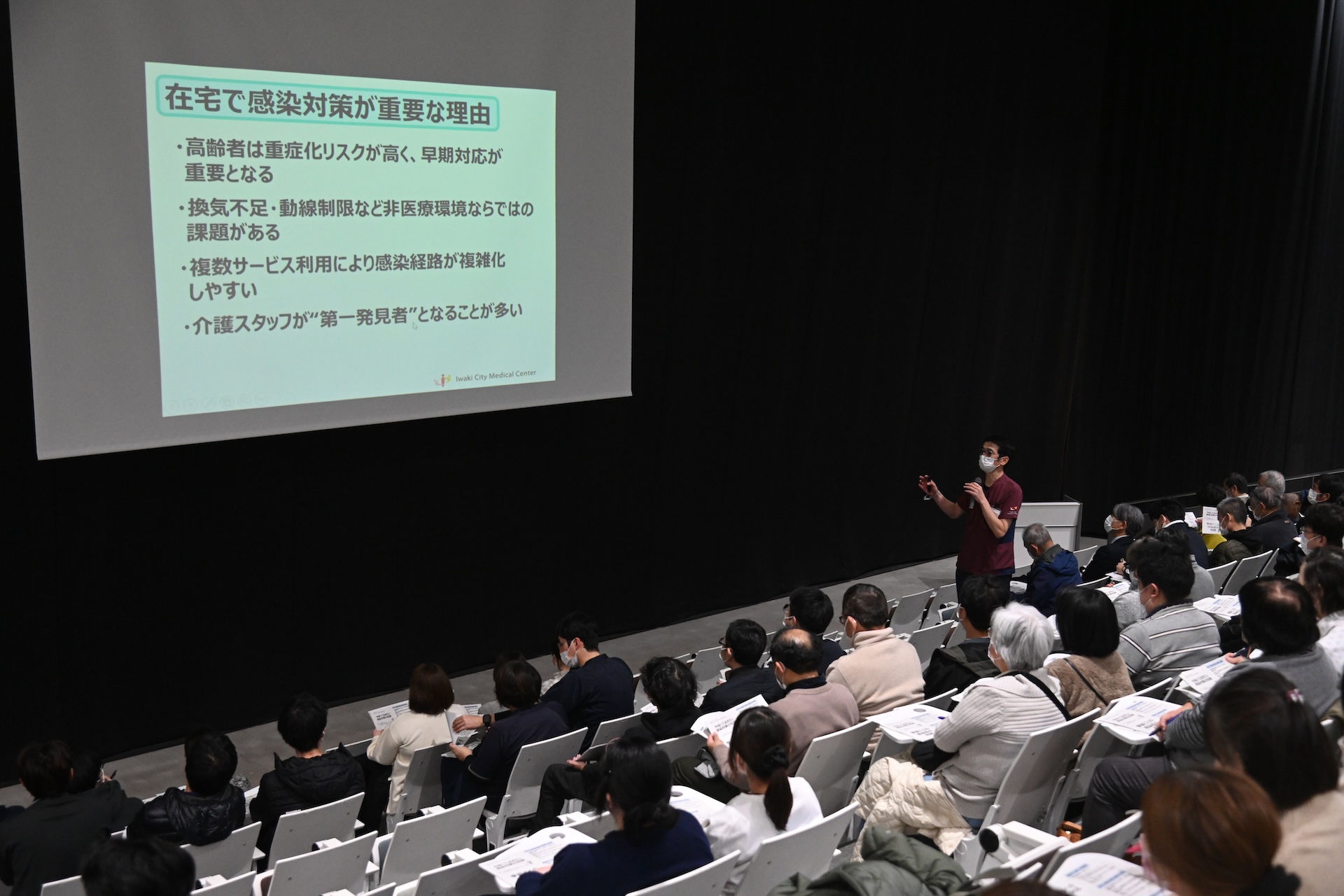医和生会(いわきかい)の若手職員が交流する「若手ラボ」がこのほど開かれました。2024年4月入職の新卒職員が後輩を受け入れる前の最後の機会。「教わる立場」から「教える立場」になる意識づけを目的に「人を育てる」をテーマに実施し、「作業の意味・理由を教える」指導法を学びました。


● 作業指導と意味指導
今回で24回目となる若手ラボは3月26日に開催しました。2024年4月入職の2人と先輩の若手職員の合わせて5人が参加。事業推進課の皆川が講師を務めました。今回のテーマは「人を育てられる人になろう」。2つのグループに分かれた参加者は、これまでに受けた「良い指導」を振り返り「意味も含めて教えてもらえた」経験を話し合いました。「ご利用者様に後ろから声を掛けない」と指導を受けた参加者は「後ろから声を掛けると驚かせてしまう」と意味も教えてもらったと発表。「机に書類を載せたままにしないように」と指導された参加者は「個人情報が人の目についてしまう」と意味も教わったといいます。

皆川は「指導には、『作業指導』と『意味指導』がある」といいます。「作業指導」は「おむつ交換は20分以内に終わらせて」といった作業や手順だけを教えることで、「意味指導」は「『恥ずかしい』という気持ちを少しでも感じさせないよう20分以内に終わらせる」という作業の意味を教えることと説明。皆川は「新卒職員も含め、『作業』はできるようになったと思う。今後は意味指導を実践してほしい」と呼び掛けました。

● なぜ、いけないのか?
ケーススタディでは「新卒職員が利用者様に『うんうん』と相づちしたり、『今行くから待ってて』といった言葉遣いをしている。どう指導するか?」を考えました。指導する側の気持ちを想像して考えた新卒の参加者は「ご利用者様が畏縮(いしゅく)する」「ご家族が見たら不快に思う」と意見。なぜその言葉遣いがいけないかを説明できるよう考えていました。別のケースでは「片手で車いすを押しながら、もう片方の手で書類を持って移動していた新卒職員にどう指導するか」。参加した先輩職員は「その新卒職員にも理由があってそうしているかもしれないからまず事情を聞いた上で、『けがにつながるから、ご利用者様の安全を第一に考えて』と指導する」と意見。「ルールだからダメ」と一方的に注意するのではなく、新卒職員の考えも聞いて指導する大切さを伝えました。

● 意味を教える3つの理由
皆川は「作業を覚えるだけではその場限りの対応になってしまい、意味まで理解できたら状況に合わせて考えて行動できる」「言われたことをやるだけなら“作業員”。『役に立っている』と実感させるためにも意味の指導が大切」「理由まで理解しなければ間違いを繰り返し、ミスや事故につながる」と、意味を教える大切さの3つのポイントを強調。「目の前の仕事にどんな意味があるか説明できる先輩になってほしい」と呼び掛けました。
医和生会では、新卒職員や若手職員を対象に、2カ月に1回「若手ラボ」という研修会を開催しています。人間性や考え方の成長を大切にし、人としての成長をサポートしています。