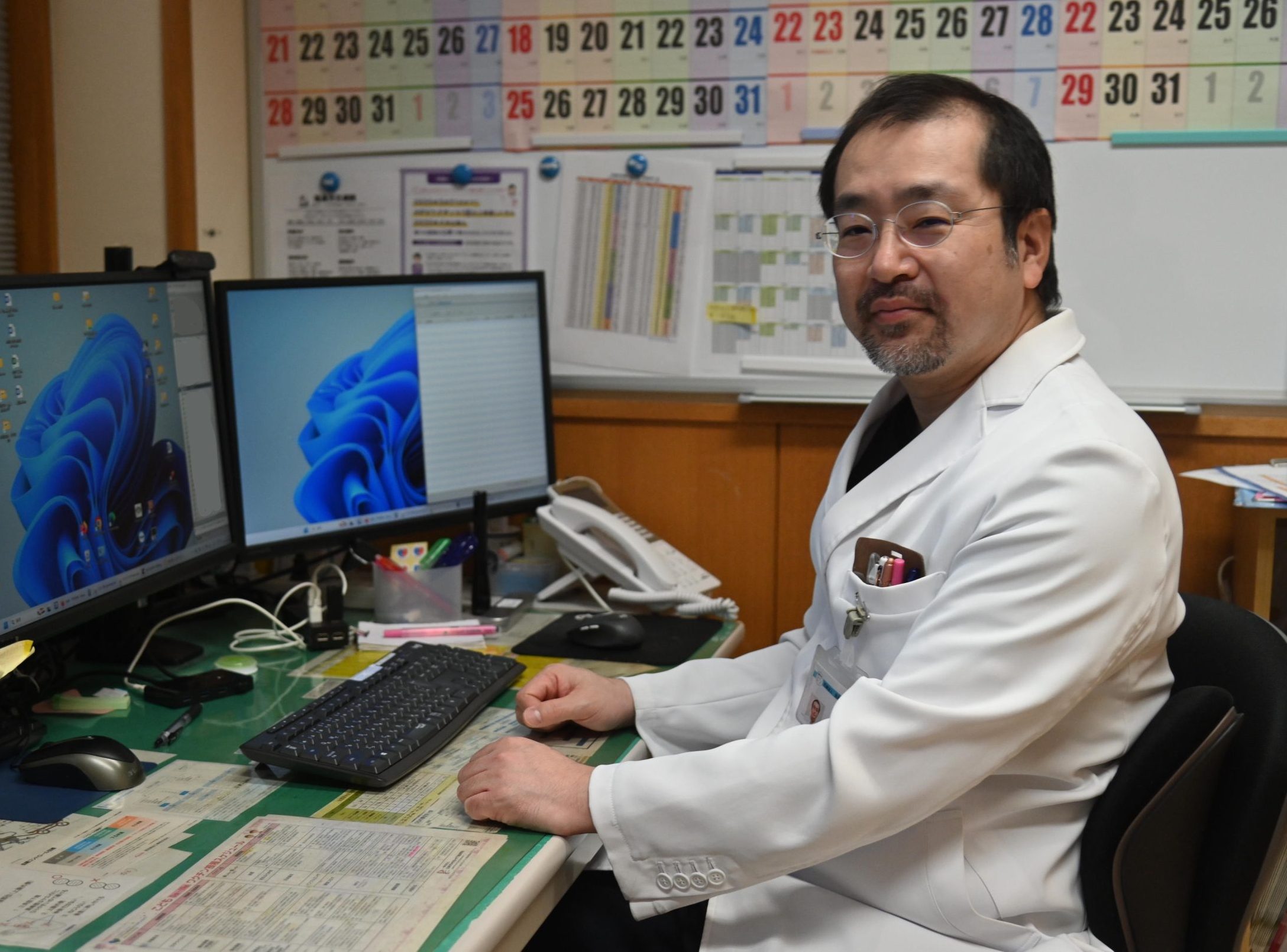「あれ?財布、どこに置いたっけ?」「人の名前が出てこない・・・」といった物忘れが増えてくると、「もしかして認知症?」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
しかし、物忘れが全て認知症という訳ではありません。
そこで、第3回では認知症に気が付くためのポイントを紹介していきます。
認知症は早期発見と適切な対応で、進行を遅らせることができるため、家族や周囲の“気付き”が重要です。
本シリーズは医和生会(いわきかい)の介護支援専門員(ケアマネジャー)で、認知症のスペシャリストでもある芳賀が、認知症に関する基礎知識や接し方、予防について、身近な体験を通してシリーズで解説します。
芳賀は「このシリーズを読むことで、認知症の人に対して不安を抱かず、優しく接するきっかけになってほしい」と願っています。
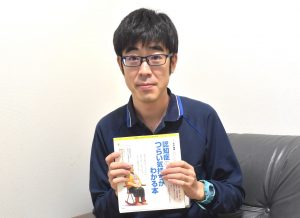
● 突然、畑仕事をやめてしまった
認知症を早期発見し、うまく改善できた例として、私の祖母を紹介します。
祖母は定期的に畑仕事をしていたのですが、ある時から畑に行かなくなりました。
ずっと椅子に座ってボーッとする毎日が続き、同居家族が「おかしい」と感じ、病院を受診したところ、初期の認知症だと判明しました。
早期発見だったため、治療薬を服用したことで、症状が改善され、少しずつ外出もできるようになりました。
● 早期発見で準備ができる
もう一つの事例を紹介します。
私のもとに、あるご家族から「うちのお父さん、認知症かもしれない・・・」という相談がありました。
ご本人(お父様)は一人暮らしをされていたそうですが、ご家族が様子を見に行くと、冷蔵庫に大量のお弁当が入っていて、不思議に思ったと言います。
私は、ご本人の自宅を訪問し、状況を確認しました。
すると、以前は毎月定期的に通院していたのに、ある時を境に通院していないこともわかりました。
早い段階で、ご家族からの相談を受けたので、病院受診や治療薬の服用、適切な介護サービスに結びつける準備を段階的に整えることができました。
● 「いつもと違う」という気づき
上記の2つの事例で共通しているのは、早い段階で「いつもと違う」と気付いたことです。
定期的にしていることをしなくなったり、当たり前にできていたことができなくなったりしたことに気付けるかどうかが重要になります。
事例にもあった畑仕事や通院のほか、毎週楽しみにしていたテレビ番組への関心がなくなって、ボーッとすることが増えた、なども認知症のサインかもしれません。
● 加齢と認知症の「物忘れ」の違い
年齢を重ねると、自然と「物忘れ」が増えます。
ただし、注意したい「物忘れ」は、通帳など普段無くさない物を失くす、いつも探し物をしている、というケースです。
認知症の場合は体験自体を忘れてしまいます。
例えば、「夕食で何を食べたのか思い出せない」というのは加齢によるものと考えられ、「食事した体験」自体を忘れるのは認知症だと考えられます。
そのほか「デイサービスの日は明日だよね?」などとすぐに何度も繰り返して確認してきたり、ヒントを伝えても思い出してもらえなかったりするのも、認知症の可能性があると思われます。
認知症のサインは、このような「物忘れ」のほか、「前よりも怒りっぽくなった」「無気力」が多いように感じます。
● 認知症の疑いを感じたら専門機関に相談を
もし、身近な人に認知症の兆候を感じたら、かかりつけ医に相談することをおすすめします。
認知症の疑いがあれば、専門医を紹介してもらい、早期診断につなげることが大切です。
ご近所の方など、直接病院とつなげない場合には、いわき市の「地域包括支援センター」に相談してみるといいと思います。
ここは、地域住民からの介護や福祉に関する相談にも対応しています。
既に介護サービスを利用中で、認知症が心配という場合は、担当しているケアマネジャーに相談すると、適切な支援につなげてもらえるはずです。
ほかにも認知症の人や家族らが集まる「オレンジカフェ」など、地域には認知症をサポートする窓口は複数あります。
● 早期発見が大事
認知症の治療薬など研究は進んでいますが、現在の医学で認知症を治すことはできません。
ですが、進行を遅らせることはできます。
そのために大切な事が「早期発見」です。
ご家族のみならず近所の方にも温かい目を向けて、みんなで認知症の疑いに気付けて、専門機関につなげられる地域になれば、「安心して暮らし続けられる地域」に、より近づくことができます。次回は認知症の人が安心できる優しい接し方を解説します。
<講師・芳賀の紹介>
医和生会居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員(ケアマネジャー)。20年以上介護の仕事に従事。認知症介護指導者養成研修の修了者であり、「認知症キャラバン・メイト」の資格も保有。
ケアマネジャーとして利用者さんの在宅生活を支える一方で、地域住民に向けて認知症への理解を広める活動にも力を入れています。
【認知症関連記事】
▶いわき市で認知症研修|認知症ケアのプロが伝える「できることを見つけるケア」
\「家で過ごせて本当によかった」その一言が、地域に寄り添う福祉の原点/
医和生会では、「在宅での暮らしを支えたい」「家族も含めて寄り添いたい」という思いを持った介護職員を募集しています。
利用者様の人生に向き合い、人と地域を結びつける介護の仕事に、あなたもチャレンジしてみませんか?
▼ 職場見学・応募はこちらから
医和生会の採用情報ページ|https://iwakikai.jp/recruit/