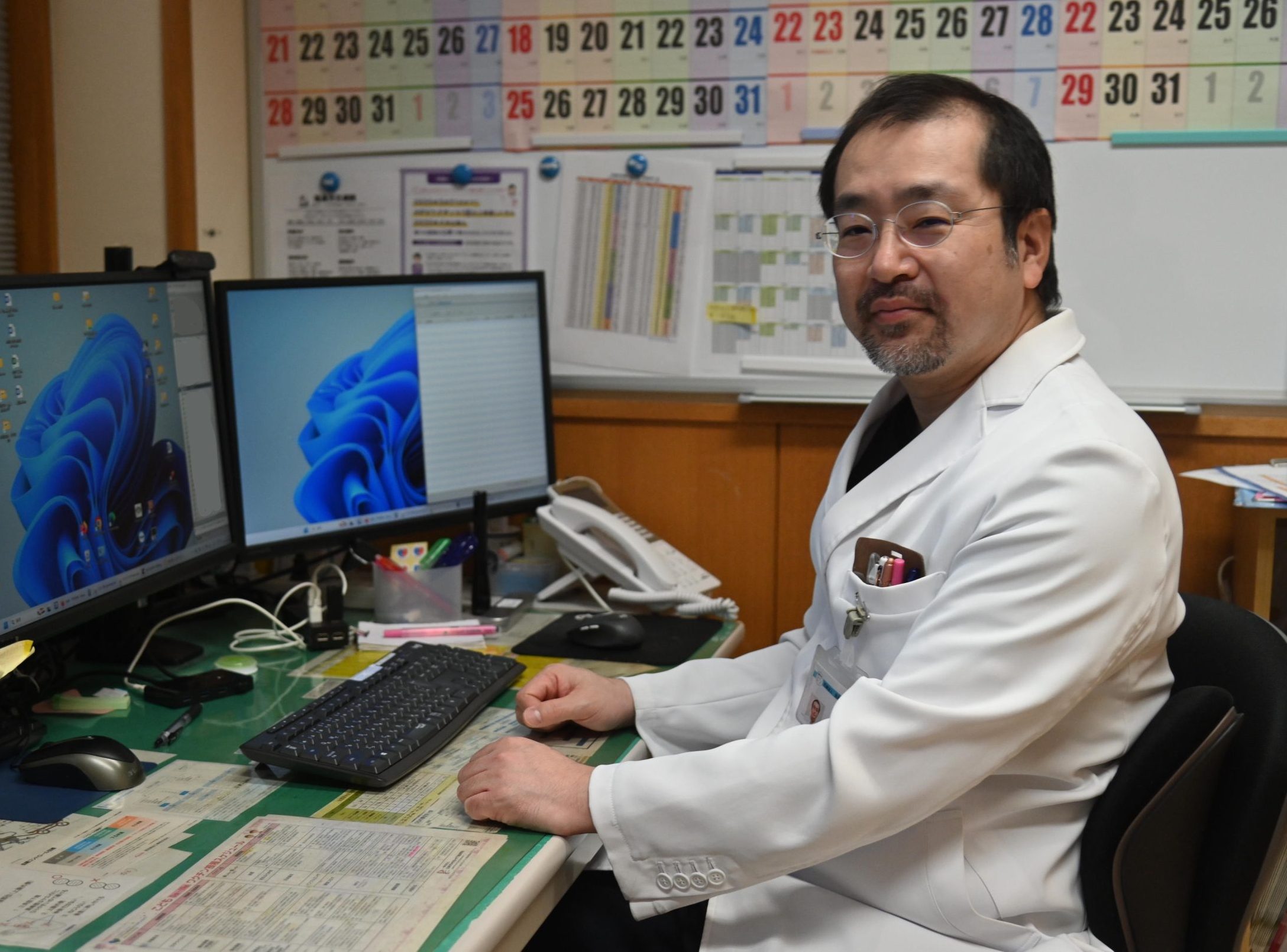いわき市平地区の医療・介護・福祉関係者が交流する「平在宅療養多職種連携の会」がこのほど、オンライン上で開かれました。訪問介護事業所の管理者が「多職種の情報共有」をテーマに事例発表。患者の緊急時にどう支援者間で連絡を取り合うか、参加者同士で情報交換しました。
● 30人が参加
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護職員、リハビリ職など30人が参加し、10月17日に開かれました。発表者は、朝、昼、夜でそれぞれ別々の訪問介護事業所を利用する寝たきり女性の事例を紹介。女性の床ずれを見つけた訪問介護士がケアマネジャーや他の訪問介護事業所などと連携、処置した数日間の支援を共有しました。

● どんなコミュニケーションツールがあるか
発表後、「初動から全事業所に情報を早く共有する方法」と「どんなコミュニケーションのツールを使っているのか」を参加者同士で情報共有しました。あるケアマネジャーは、身寄りのない緊急対応が必要な患者に限り、本人の許可を得た上でLINEグループを使い、タイムリーに処置をしてもらっていると紹介。訪問看護師は「まずケアマネジャーに電話連絡し、各事業所に伝えてもらっている」と答えました。
薬剤師は、連絡ノートを患者宅に置いて書き残して他事業所と情報共有しているとも。同様にノートでやり取りしているという訪問ヘルパーは「ケアマネジャーからノートを確認してから支援するよう指示を受けている」と紹介。指示には「この薬をこの時間に服用させる」といったものがあるといいます。あるケアマネジャーは「LINEグループは会社で禁止されている」といい、その代わりに、全国の医療介護現場で利用されているコミュニケーションツール「MCS(メディカルケアステーション)」を使っていると紹介。「看取りのケースで便利だった」と話しました。最後、同多職種連携の会の山内俊明会長(山内クリニック院長)が次回の案内をして締めました。
<平在宅療養多職種連携の会・関連記事>
「在宅患者の緊急対応を考える」
「いわき市の地域医療の課題を学ぶ」
「データ連携、介護報酬を学ぶ」
「口腔の健康チェック 専用シートで確認法学ぶ」
「低栄養が課題の支援事例」
「人生すごろくを体験」
「心不全を考える」